丹生川上神社上社は丹生川上神社3社の1つ!
| 主祭神 | 高龗大神(たかおかみのおおかみ) |
| 社格等 | 真言宗室生寺派 |
| 創建時期 | 宝亀年間(770年 – 781年) |
丹生川上神社上社について
| 観光地名 | 丹生川上神社上社 |
| 住所 | 奈良県川上村大字迫167 |
| 電車・バスでのアクセス | ●東京・名古屋方面から 近鉄名古屋…… 近鉄特急 (約2時間50分) ……大和上市…… バス (約30分) ……湯盛温泉・杉の湯…… 徒歩 (20分) ●京都方面から 京都…… 近鉄特急 (約1時間35分) ……大和上市…… バス (約30分) ……湯盛温泉・杉の湯…… 徒歩 (20分) ●大阪方面から 大阪阿部野橋…… 近鉄特急 (約1時間10分) ……大和上市…… バス (約30分) ……湯盛温泉・杉の湯…… 徒歩 (20分) ●和歌山方面から 和歌山…… JR (約1時間30分) ……吉野口…… 近鉄特急 (約20分) ……大和上市…… バス (約30分) ……湯盛温泉・杉の湯…… 徒歩 (20分) ※上記時間には待ち時間は含みません。 ※所要時間は時間帯等により異なる場合があります。 ※平成27年10月1日より奈良交通バスの路線が廃止になり、代替交通として川上村やまぶきバス、吉野町スマイルバス、南部地域連帯コミュニティバス「R169ゆうゆうバス」が運行されます。詳しくは、川上村役場または奈良交通株式会社へお問い合わせください。 |
| 車でのアクセス | ●名阪国道 針インターから……………………………約1時間30分 ●京奈和自動車道 橿原北インターから………………約1時間20分 ●京奈和自動車道 五條北インターから………………約1時間10分 ●南阪奈道 葛城インターから…………………………約1時間20分 |
| 駐車場 | 境内に無料駐車場有 |
| 入館、拝観料など | – |
| 拝観時間 | – |
丹生川上神社上社は村とともにダムに沈んだ神社
川上村を回ってるときに、こちらの丹生川上神社上社に来ました。

丹生川上神社上社は、吉野川が流れる谷から少し上がったところにある神社です。こちら実はダムができる前は谷にあったのですが、ダム建設で村と一緒に沈むことが決まり神社跡の中腹に再建されました。
ダムに沈む前に発掘調査が行われて、宮の平遺跡が発掘されました。本殿跡真下から、自然石を敷き並べた祭壇跡が出土し、また付近では縄文時代(約4000年前)の祭祀遺跡(環状配石遺構)が出土この「宮の平遺跡」は縄文時代早期の大規模集落跡と判明し、古代から人の住まう土地だったのです。
また、神社の方にお話しをお伺いしたところ元々谷にあったときは向かいの山がご神体だったそうで、龍神様が現れたそうです。



関西では非常に珍しいストーンサークルがあった!?
丹生川上神社上社は、元あった場所は大滝ダム建設時に沈んだのですが、大滝ダム建設中に宮の平遺跡が発掘されましたが、ここは縄文時代からお祈りをした場所だったそうです。
この場所、ちょうど山と山の谷あいにあり、吉野川、紀の川から太平洋にそそぐ源流域でもあり、宗教的にも重要な場所だったのだと思います。
そんな宮の平遺跡があった場所から30センチほどの直立したままの石棒が当時のままの姿で発掘された。このほかにもやや傾いたままの石棒が2基、磨石、石皿、などの他に環状配石遺構(ストーンサークル)も発見された。
ストーンサークルは国内でも珍しく、多いのは東北と北海道の地方で大陸から渡ってきたウラル系遼河文明人が作ったのではないかと思います。しかしなぜ関西のしかもこんな山奥からも発見されたのかは、謎の部分が多いと思います。
個人的意見ですが、その後奈良は日本の首都になり中枢部分になることからもわかるとおり、大陸から黒潮の流れを使って渡ってくる人間は縄文時代以前からいたのではないでしょうか。その渡来系の人によりストーンサークルのような祀りなどが伝来したのではないかと考えます。

また、最近のブームもあるのか御朱印帳が売っていたのですが、なんと吉野杉を使って作られた御朱印帳だそうで、これは絶対買っておかないといけないぞ!と龍神様が言ったような(妄想)気がしたので購入しました。

こちらの社へ行くには、杉の湯近くから登り道があります。見晴らしもよく綺麗な神社、丹生川上神社上社、奈良観光するならぜひ行っていただきたい場所です。

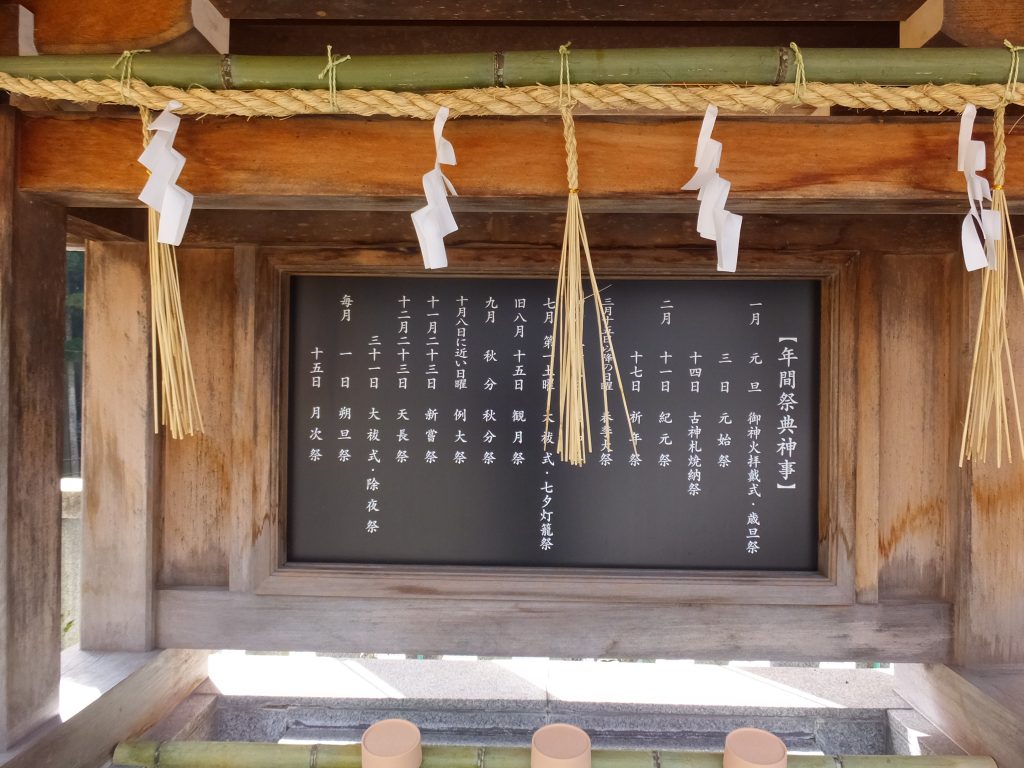




2022年秋の紅葉風景
2022年11月下旬に改めて丹生川上神社上社に来ました。この日は晴天で暖かくて最高でした。紅葉ももう終わってると思ったらとてもいい感じ!
平日ということもあって参拝客は1人もいなかくて、余計に厳かさが強調されてました。ゆっくり見るなら平日が一番!














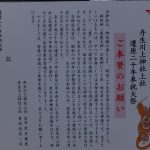





















コメント